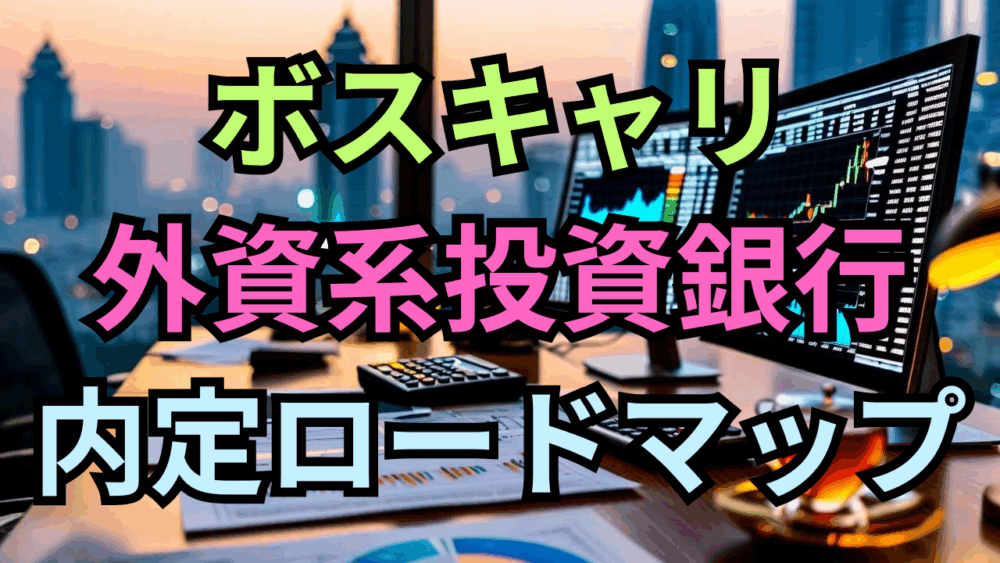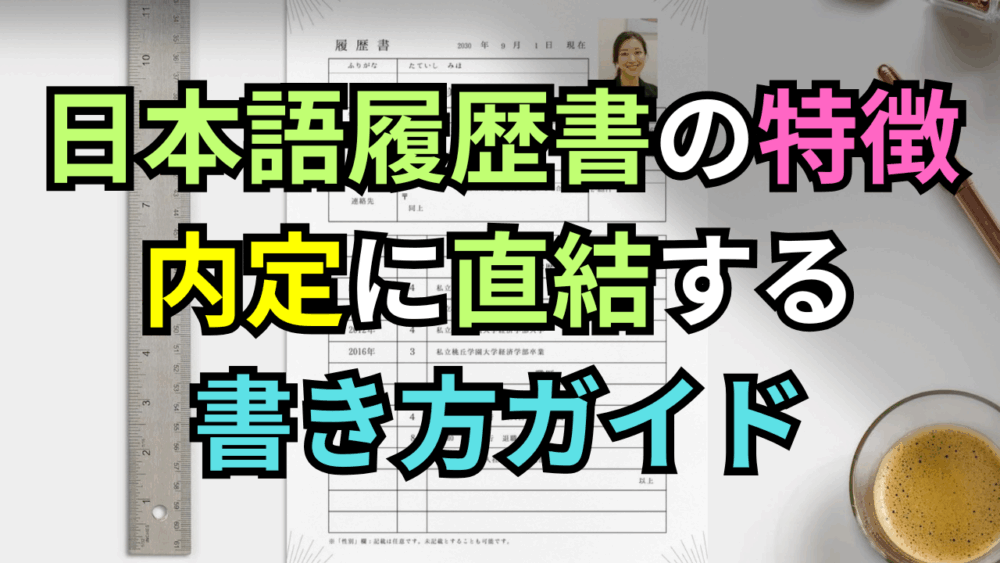日本の大学に通う学生がボストンキャリアフォーラムに参加しようとすると、参加資格の一つである交換留学に行く必要が出てきます。今回の記事では、コロナ後、日本の大学生の交換留学はどう変わったか?について解説します。
コロナ後、日本の大学生の交換留学はどう変わったか?
新型コロナウイルスの世界的な流行は、留学制度に大きな影響を与えました。特に日本の大学における「交換留学プログラム」は、2020年から一時中断・縮小を余儀なくされ、長らく再開の目処が立たない時期が続きました。
しかし、2022年以降、各国の入国制限が大幅に緩和されたことで、交換留学は本格的に再開し、活気を取り戻しています。2025年現在、日本の大学からの交換留学には以下のような顕著な傾向と変化が見られます。
1. 留学希望者数はコロナ禍以前を上回る水準に回復
文部科学省や大学の国際部門の発表によると、コロナ禍で一時的に激減した日本人学生の海外留学希望者数は、2024年には2019年の水準を大きく上回り、2025年もその勢いは持続しています。背景には、海外経験への強い憧れに加え、オンライン留学で得た経験を活かしたいという意欲の高まり、そして円安にも負けないグローバル志向の学生の増加が挙げられます。
2. 行き先の多様化と英語圏・欧州の人気は依然として高い
以前は東アジアへの留学も根強い人気がありましたが、現在では英語圏(アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド)に加え、北欧(フィンランド、スウェーデン、ノルウェー、デンマーク)、西欧(ドイツ、フランス、オランダ)などへの志向が一段と強まっています。これらの地域は、質の高い教育水準に加え、比較的安定した社会情勢が評価されています。一方で、経済的な負担を考慮し、物価の比較的安い国や奨学金制度が充実している国を選ぶ学生も増えています。
3. オンライン留学・ハイブリッド型は定着し、選択肢が多様に
コロナ禍で急速に普及したオンライン留学、そしてオンラインと対面を組み合わせたハイブリッド型留学は、現在では一般的な選択肢として定着しています。多くの大学が、学生のニーズに合わせて多様なプログラムを提供しており、例えば、短期のオンライン集中講座、特定の専門分野を深く学べるオンラインプログラム、海外大学の正規課程の一部をオンラインで履修できる制度などがあります。ハイブリッド型では、前半をオンラインで準備し、後半に現地で実践的な学びを深めるなど、効果的な学習が期待されています。
4. 留学とキャリア形成の連携がより明確に
留学は単なる異文化体験ではなく、将来のキャリア形成に不可欠なステップとして捉えられる傾向がますます強まっています。具体的には以下のような動きが活発です。
- 専門分野との連携強化:大学の学部・学科と連携し、専門知識の深化や研究活動への参加を目的とした留学プログラムが増加。例えば、工学部と提携した海外大学での研究インターンシップ、経済学部と連携した金融機関での実務研修など。
- インターンシップ・ボランティア活動の組み込み:単位認定されるインターンシップやボランティア活動を留学プログラムに組み込むことで、実践的なスキル習得と異文化理解を同時に深める試み。
- デュアルディグリープログラムの拡充:海外大学との共同学位取得プログラムが増加。学部レベルだけでなく、大学院レベルでの連携も進んでいます。
5. 大学・政府による経済的支援と留学促進策が進化
円安の影響を受け、留学の経済的負担が増している現状に対し、大学や政府は様々な支援策を強化しています。
例えば:
- 大学独自の奨学金制度の拡充:派遣留学だけでなく、オンライン留学やハイブリッド型留学を対象とした奨学金制度を設ける大学が増加。
- 官民連携による奨学金プログラムの新設・増額:日本学生支援機構(JASSO)の奨学金に加え、企業や財団による留学支援プログラムが多様化。特に、特定の専門分野や地域への留学を支援する奨学金が登場しています。
- 留学費用のローン制度の整備:学生が安心して留学に挑戦できるよう、低金利の留学ローンを提供する金融機関との連携を進める大学も出てきています。
- 政府の留学促進キャンペーンの展開:「トビタテ!留学JAPAN」のような官民協働の留学促進キャンペーンが継続的に実施され、留学の意義や魅力を発信するとともに、奨学金情報などを集約したプラットフォームが整備されています。
【大学プログラム例】
- 東京大学 グローバルパートナーシップ研究員プログラム:海外の有力大学院と連携し、修士・博士課程の学生が一定期間、相手校で研究活動を行うプログラム。研究指導に加え、異文化理解や国際的なネットワーク構築を支援。
- 早稲田大学 グローバルエデュケーションセンター 短期海外研修:語学学習だけでなく、特定のテーマに基づいた海外研修プログラムを多様な国・地域で展開。近年は、SDGsや地域課題解決をテーマにしたプログラムも増加。
- 慶應義塾大学 国際交流プログラム: 世界各地の提携大学との交換留学に加え、サマープログラムや海外インターンシップなど、多様なプログラムを提供。学生の目的に合わせたカスタマイズが可能。
- 京都大学 国際高等教育院 国際教育交流部門:派遣・受入プログラムに加え、オンラインでの国際交流科目を多数開講。海外大学との共同ワークショップやディスカッションを通じて、異文化理解と協働力を育成。
【奨学金制度例】
- 日本学生支援機構(JASSO)海外留学支援制度(貸与型・給付型): 経済状況や留学計画に応じて、様々な種類の奨学金を提供。長期留学だけでなく、短期留学やオンライン留学も対象となる場合があります。
- トビタテ!留学JAPAN 新・日本代表プログラム: 意欲と能力のある学生の海外留学を支援する給付型の奨学金プログラム。多様な分野での留学計画を募集。
- 各大学独自の奨学金: 多くの大学が、交換留学や私費留学を支援するための独自の奨学金制度を設けています。派遣先の地域や期間、学業成績などによって支給条件が異なります。
- 民間企業・財団の奨学金: 特定の分野や地域への留学、または特定の大学への留学を支援する民間企業や財団の奨学金制度も多数存在します。
まとめ:留学は“自己成長のエンジン”へ
コロナ禍を経て、日本の交換留学は単なる語学学習や異文化体験に留まらず、グローバルな視点と専門性を磨き、将来のキャリアを戦略的に築くための重要な機会へと進化しています。学生一人ひとりの目的やニーズに合わせた多様なプログラムと、経済的な負担を軽減するための支援体制が充実しつつあり、**“迷う留学”から、“主体的に選び取る留学”**へと成熟しています。
これから交換留学を目指す学生の皆さんにとって、綿密な情報収集と周到な計画はこれまで以上に重要です。大学の国際交流センターやキャリアセンター、そして各種支援制度を積極的に活用し、グローバル社会で活躍するための第一歩を踏み出してください。
ボストンキャリアフォーラムとグローバル企業への就職もその延長線上にあるはずです!